「設立10周年記念 こどもの貧困解消へ!2ndステージ開幕式」を6月14日(土)午後、主婦会館プラザエフ(東京都・千代田区)で開催しました。
この10年間お支えいただいたみなさまを中心に、「子どもの貧困対策推進議員連盟」会長の田村憲久・衆議院議員(元厚生労働大臣)、「あすのば子ども・若者委員」も含め171人の方にご参加いただきました(オンライン含む)。
会場には、石破茂・内閣総理大臣からのメッセージも届き披露されました。
「昨年6月には、超党派子どもの貧困対策推進議員連盟が中心となって、『子どもの貧困対策法』を改正し、法律名に『こどもの貧困の解消』が明記され、国のこどもの貧困解消に向けた取り組みが強化されることになりました。この法律の改正には、ほとんどの国会議員が賛成しましたが、このことは、あすのばさんが、生活困窮に苦しむ子育て家庭に寄り添い、その実態を国会議員に粘り強くお伝えいただき、立法府を動かしてくださったご努力の賜物と存じます。これからも、子育て家庭に寄り添い、こどもの貧困解消に必要な施策を提言いただくことをご期待申しあげます。そして、一日も早く、我が国からこどもの貧困が解消されるよう、政府挙げて真剣に取り組んでまいります」と、大変心強いメッセージをいただきました。
開幕式のテーマはバトン。
赤いバトンを握った小河光治・あすのば代表理事のあいさつで開会しました。
「あすのば設立直後に、ある若者からこんなことを聞かれたんです。
『あすのばの最終目標ってなんですか?』
私は即座に『解散です』と答えました。あすのばのビジョンは『こどもの貧困をなくすこと』ですから、この課題をなくして解散することがゴール。そういう思いでやってきて10年経ちましたが、まだまだ道半ばです。
この10年を振り返ると、あすのばだけではできなかったことばかり。みなさんとスクラムを組んでやっていただいたことに厚くお礼を申しあげ、セカンドステージもさらに協働して前進したい」と述べました。

赤いバトンは「子どもの貧困対策推進議員連盟」の田村憲久会長へ。
子どもの貧困対策推進法の成立時、厚生労働大臣だった田村会長は、これまで、こどもの貧困解消に向け最もご尽力いただいた国会議員のお一人です。
田村会長のごあいさつでは、昨年末の石破総理への要望や今月の各省庁への申し入れや「骨太の方針」にこどもの貧困解消のための文言を盛り込むことなどにおいて、あすのばなど民間団体の取り組みを高く評価いただきました。とくにひとり親世帯の住まい・就労支援、養育費の確保、児童扶養手当の所得要件の見直しなどを早期に実行することの重要性について発言し、「こどもの貧困をなくすことが一丁目一番地だ」と述べられました。

続いて、長年にわたって子どもの貧困対策推進議員連盟の中核として力を尽くしてこられた前法務大臣の牧原秀樹さんに、バトンタッチ。
牧原さんは、「(法改正など)政治をこれだけ動かしているということは、すごく稀なことです。あすのばさんの10年は、日本史に残るぐらい輝かしい取り組みであり、みなさまお一人おひとりがそこに関わっていたことを誇りに思っていただきたい。これからの10年、みなさまの活動一つひとつが、これから生まれてくる子どもたちにとって、希望の光になることは間違いないと保証させていただきます」と述べました。

また、公明党顧問で元議連副会長だった古屋範子さんにもお越しいただき、ごあいさつをいただきました。
古屋さんは、「私も、子どもの貧困対策法の成立から関わり、その後、2度にわたる法改正を行えたのは、あすのばのみなさまがいたからこそ、と思います。ひとり親の税制改正の壁が厚く、何年もやりながら、みなさまの後押しがあって、やり遂げることもできました。給付型の奨学金、児童扶養手当の拡充、こども基本法の成立もみなさまが、どれだけ足を運んで後押しをしてくださったか、その結果だと思っています」と評価いただきました。
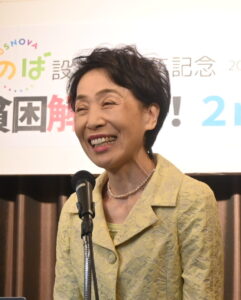
さらに、元文部科学大臣の下村博文さんからは「ここにいるみなさんが苦労に苦労に苦労を重ねて今日があることに対して心から敬意を申しあげたい。つらい思いを持っている子どもたちが増えるような社会じゃなく、子ども視点で、まさにあすのばの精神そのものだと思いますが、物心ともに子どもたちが輝いて、そして、未来に対して夢と希望を持てる社会を私たちが、私が、作らなくちゃいけないと改めて感じさせていただきました」と述べました。
なお、総理大臣補佐官で衆議院議員の長島昭久さん、立憲民主党・衆議院議員の山井和則さん、国民民主党・衆議院議員の石井智恵さん、東京都立大学教授で「子ども・若者貧困研究センター」センター長の阿部彩さんからも温かいメッセージをいただきました。

高校生、大学生世代の若者で構成される子ども・若者委員会から「”こわか”る」と題して、子ども・若者委員会の理念や活動について発表を行いました。子ども・若者委員会は、こどもたちの声を見過ごすことなく社会に繋げていきたいという思いから「声を紡ぐ」を理念に掲げ活動しています。合宿ミーティングや小中合宿キャンプ、全国集会、フィールドワークやヒアリング調査など、こどもの貧困解消に向けた10年間の活動を振り返りました。

パネルディスカッションでは、子ども・若者委員会として活動してきた若者らが、貧困や活動について思いを語りました。
最初のテーマは「『貧困』と自分」。3人の子ども・若者委員が、それぞれの原体験や、「こどもの貧困」に関心を持ったきっかけについて話しました。阿部彩教授の著書をきっかけに「こどもの貧困」に関心を持った大学生の其部さんは、「9人に1人」という日本の相対的貧困率の高さに「衝撃を受けた」と語ります。「お金がないから友だちと遊びに行けない」、「お昼も食べれない」という友だちがいたことで、身近な問題として関心を持ち、子ども・若者委員になったとのことでした。
また、社会人の中村さんは子ども・若者委員会に入ったことで、「自分の置かれていた環境や、仕方がないって飲み込んできたことや、これも諦めなくてもよかったのかもしれない」と、「他の選択肢もあったのかもしれないということに気づいた」ことで、自分の過去の経験が「腑に落ちた」ことで、貧困への関心を持ったと語りました。

2つ目のテーマ、「活動を通じて感じたこと」で高校生の岩浪さんは、あすのばの小中キャンプでの経験を語り、「普段崖っぷちで戦っているような、毎日毎日戦い続けているような子どもたちが、2泊3日だけは安心して過ごせるから笑顔になる」と思い返す一方で、「でもそれって2泊3日だけで、家に帰ったらまた同じような状況に戻ってしまう」ことを指摘し、「支援の強化」の必要性を求めました。また、「あすのばが10周年でこれから2ndステージというふうになっているけど、僕がすごく思うのは2ndステージをあと10年やるのかというところ。あと10年やってたらここにいる子若も大人になってしまう。もっとスピード感を持った対策が必要」と強い思いを伝えました。
続いて「貧困とこれから」というテーマでは、其部さんは、「貧困対策法成立から12年経ち、支援が増えてきたものの未だに苦しい思いをしている人がたくさんいる。支援を当事者にどう届けていくかについて再考する必要がある」と訴えました。中村さんは「私が若者の期間を過ごしている間に法律や制度が増えてきた。でも私自身の目線で、何が変わったと言ってもわからない。子どもはずっと子どものままではない。今、困難を抱える子に届く支援が必要だ」と見落とされがちな「今」に焦点を当てた支援の必要性を訴えました。
コーディネーターを務めた大学生の髙山さんは、「6千人調査での回答者の記述を見ていると『努力しても意味ない』みたいな感情が今の社会にある。金銭面でも心の面でも、『自分が努力すれば叶えたいものが叶う』と子ども・若者が思える社会になってほしい」と締めくくりました。
パネルディスカッションは細かいリハーサルや、台本を用意した企画ではありません。「子どもたちが貧困で夢を諦めないでほしい」と思い、集まって行動している子ども・若者委員会では日常の話し合いの様子を参加者の方々にご覧いただきました。

パネルディスカッションでもお伝えしたような問題意識を持ち、「こどもの貧困をなくす」ために活動する子ども・若者委員会がこれからの1年間取り組む活動の計画の発表も行いました。活動の成果報告は、来年6月に行う予定の全国集会で行います。あすのばが行った6千人調査の中に、不登校になった子の居場所が少ないという内容の自由記述があり、この意見に共感する子ども・若者委員が多かったことから、今回のテーマは「学校に行っていない子と親」となりました。不登校の子と親は、それぞれ社会からの孤立や仕事にいけないなどの課題を抱えています。この課題解決にはサードプレイスの存在が重要なのではないかと考える一方で、全国の不登校の子どもたちがサードプレイスに繋がることができていない現状があります。子ども・若者委員会では、このような現状の背景を明らかにするために、ヒアリング調査やフィールドワークを行う予定だと発表しました。

あすのば設立から10周年を迎える本年、これまでのあすのばの歩みをまとめた「10周年記念紙(後日HP上で公開予定)」を作成しました。
それぞれの事業を担当している職員一人ひとりから、これまであすのばが行ってきた取り組みなどについてご報告をさせていただき、これからの「中期計画(後日HP上で公開予定)」の発表も行いました。

・近藤博子さん(一般社団法人ともしびatだんだん代表理事)
・直島克樹さん(川崎医療福祉大学医療福祉学部講師)
・深堀麻菜香さん(元あすのば子ども・若者委員/認定特定非営利活動法人おてらおやつクラブ職員)
・李炯植さん(認定特定非営利活動法人Learning for All代表理事)
以上の4人のパネラーに「こどもの貧困解消に必要なこと」について議論していただき、朝日新聞記者の中塚久美子さんにコーディネーターを務めていただきました。

「本来公助として公的機関がやるべきところが、『おたがいさま』のネットワークに頼るようになってきた」
「子ども食堂が広がるにしたがって、子ども食堂の役割がどんどん増えてきてしまった。当初は、隣のおばちゃんが隣の子どもにたくさん作った煮物を渡してあげるとか、そういう地域のつながりができればいいな、という思いで始めたのに、『プラットフォームになる』、『最初の相談窓口』、『困りごとを抱えた世帯の発見場所』、『地域の拠り所になる』など、さまざまなことがのしかかってくるようになってしまった」と話す近藤さん。また、「(行政から)紹介されてくるハードなケースが増えた」という実態もあるそうです。
続く直島さんも「『行政から紹介されてきました』というケースは、地域ではたくさんあります。行政の方も異動で、いきなり相談にのった家庭の現状を変えようと思ったときに、『地域でこういう(子ども食堂のような)場所があるよ』となると、どうしてもまずそこに行く」とのこと。地域では「子どもの支援を経験したことがある人、専門的な資格を持った人が少なくて、なかなかネットワークを立ち上げることは困難」で、行政についても「非正規雇用での担当者の方が多いということが結構ある」と、岡山の実例を踏まえて連携の難しさについて語りました。
深堀さんからは「北海道は二重行政のような部分もあり、制度や手続きによっては『札幌だけ別枠』『この手続きは道』『これは市』など複雑に違う」と北海道の実情を述べた上で、行政の連携との難しさを述べられました。また、「公助・共助っていうけれど、共助の中に行政の人たちも一緒に入ってもらって共にやっていけないのか。民間の人たちだけで頑張りましょうということではなくて、みんなで知恵を絞って使える制度だったりとか、できることを考えていけたらいいのでは」といった問題意識を述べました。
李さんからは、民間の役割、行政との関わりについて、「ご寄付によって居場所や学習支援をやればやるほど自治体が手を引いてしまう。共助があることによって公助が衰退する」との指摘があり、「困難な環境にあるお子さんの環境整備については、公助がもっと拡大すべき。公助がしっかり拡大した上での共助ではないか」などといった課題を述べました。また、民間の連携や行政との関わりについては、「理想的にはスイミーみたいな感じで小さいけど、つながって大きくなる。子どもの権利を守るために政治を動かすような影響力を持つのが大事だと思っている」と語りました。
約90分間の充実した議論を踏まえ、最後に中塚さんから「こんなに熱心にこどもの貧困を何とかしたいと遠方からも学ぼうと思っている方々が、全国にこんなにいることは、私も仕事を続ける原動力になっています。今日も100人以上の方が土日を使われて東京に集まり、オンラインでアクセスし、自分たちの課題のブレイクスルーを見つけようと思っていらっしゃる。このみなさんと手をつないで、今、目の前にある壁を乗り越えていきたい」と締めくくりました。

参加者のみなさんから、多くのメッセージをいただきました。一部をご紹介します。
▼若者が言っていたように、いまからまた10年したら、子どもはオトナになってしまう。しかし、特効薬はなくても動きを止めたら終わり。だから私たちは歩き、時には走りながら進めなくては、と思いました。あすのばさんの強い想いを応援します。
▼いま、こどもたちの状況はさらに厳しくなっていると思います。セカンドステージで、こどもが大人になる前にこの国の社会の仕組みが変わるような活動を、多くの皆さんと連携して発信し続けてください。
▼あすのばさんのチームワークの骨組みがぐんぐん太く強くなっていらっしゃるご様子
に、10年の歳月の重みとたゆまない情熱が見える思いでした。「まずは」の10年、本当にお疲れさまでした。「子若」の皆さんのお話には目が覚める思いで、1日の中で何度か思い返しては自分に何ができるかを考えています。
▼私も、自分の活動がなくなることが夢だといつも話していて、同じ貧困の支援をしている人たちは同じ想いなんだなと思い、胸があつくなった。日々のさまざまな子どもたちに出会う中で自分たちでは限界だと感じるときもあり、もっと今以上に「公」との連携が必要だと思いました。